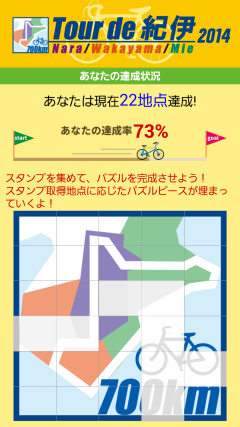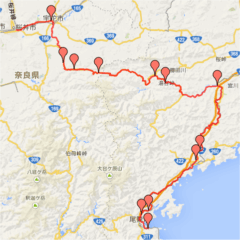どうやらお天気は快方に向かう様で、少し雨もおさまってきたので6時過ぎに宿を出発し、既に2008年に履修済ですが直江津町道路元標へ立ち寄ります。
どうやらお天気は快方に向かう様で、少し雨もおさまってきたので6時過ぎに宿を出発し、既に2008年に履修済ですが直江津町道路元標へ立ち寄ります。 履修済みの津有村道路元標を経て高士村道路元標へ向かう道すがらレトロ風の建物が、「前島記念館」とあります、あの1円切手の前島密かな。 やはり前島密、出生地だそうで郵政博物館別館となっています、今は開館時間中ではないのですが、こうやってサイクリング中に偶然見つけた史跡とかに気軽に立ち寄って見学して行ける時間のゆとりがほしいです、目的地をこなして行く様なサイクリングをやっている様ではまだまだあきまへん。 何枚か写真を撮って、先を急ぎます。
履修済みの津有村道路元標を経て高士村道路元標へ向かう道すがらレトロ風の建物が、「前島記念館」とあります、あの1円切手の前島密かな。 やはり前島密、出生地だそうで郵政博物館別館となっています、今は開館時間中ではないのですが、こうやってサイクリング中に偶然見つけた史跡とかに気軽に立ち寄って見学して行ける時間のゆとりがほしいです、目的地をこなして行く様なサイクリングをやっている様ではまだまだあきまへん。 何枚か写真を撮って、先を急ぎます。  高士村道路元標を経て櫛池村道路元標へ、今日は基本的に頚城平野の中をの平坦路を巡る予定なのですが、昨日の上早川村の様に少し谷あいに入った場所もあり、ここでは標高189mまで登る事に。 ここの道路元標は有形文化財に指定されている様で、「旧櫛池村役場前に設置されていた。 測量技術の開発されなかった時代の市町村を代表する『元標』で貴重なものである。 」と記した案内が並んで建っています。 記載の内容はともかく、こう云った形で「道路元標」が認知されているのは嬉しいものです。
高士村道路元標を経て櫛池村道路元標へ、今日は基本的に頚城平野の中をの平坦路を巡る予定なのですが、昨日の上早川村の様に少し谷あいに入った場所もあり、ここでは標高189mまで登る事に。 ここの道路元標は有形文化財に指定されている様で、「旧櫛池村役場前に設置されていた。 測量技術の開発されなかった時代の市町村を代表する『元標』で貴重なものである。 」と記した案内が並んで建っています。 記載の内容はともかく、こう云った形で「道路元標」が認知されているのは嬉しいものです。  次の牧村道路元標までは直線距離では2キロ程の位置なのですが、一つ北側の谷筋になり、山越えの道は積雪期通行止となっています、即ち除雪してませんよとの事です、つまりこれだけの雪が積もっている訳です。 登ってきた道を下る事に、しかし下りの寒い事と云ったら。
次の牧村道路元標までは直線距離では2キロ程の位置なのですが、一つ北側の谷筋になり、山越えの道は積雪期通行止となっています、即ち除雪してませんよとの事です、つまりこれだけの雪が積もっている訳です。 登ってきた道を下る事に、しかし下りの寒い事と云ったら。  一度平野部に戻って再び登りへ、道路元標は元の牧村役場、現在の上越市牧区総合事務所前に保存されているとの事なのですが。 懸念していた事が、念のために穴蔵さんと国道901号さんのサイトで確認してみますが、どうやらのこの雪の中に間違いなさどうです、さすがにこれでは手の出しようがありません。
一度平野部に戻って再び登りへ、道路元標は元の牧村役場、現在の上越市牧区総合事務所前に保存されているとの事なのですが。 懸念していた事が、念のために穴蔵さんと国道901号さんのサイトで確認してみますが、どうやらのこの雪の中に間違いなさどうです、さすがにこれでは手の出しようがありません。  意気消沈してすごすご再び登ってきた道を下る事に、ところでお天気の方ですが雨こそ止んだものの、ときおり霙の様なものが襲ってきます。 写真は北国の冬の光景ですね、なかなかの「自撮り」ポイントなのですが三脚は小型のスタンド程度のものを持ってきているだけなので、どこか高さの稼げるところがあればと思っていたのですが、チャンスはありませんでした。
意気消沈してすごすご再び登ってきた道を下る事に、ところでお天気の方ですが雨こそ止んだものの、ときおり霙の様なものが襲ってきます。 写真は北国の冬の光景ですね、なかなかの「自撮り」ポイントなのですが三脚は小型のスタンド程度のものを持ってきているだけなので、どこか高さの稼げるところがあればと思っていたのですが、チャンスはありませんでした。  道路元標の位置情報はGPSに登録してあるのですが、上杉村道路元標、ちかくまで来ているのですが回りをウロウロしている様で、なかなか見つけられません。 もしやあそこに見える二宮金次郎像の前にあるのは!? 資料を確認すると間違いなさそうです、小学校の中庭の様なのですが、柵とかはありませんしどちらから回っても雪の中を行くしかなさそうですので、強行突破です。 さすがにスパッツまでは用意していませんでしたが、替えのニッカホースもありますし、案の定50cm位は埋まってしまいました。
道路元標の位置情報はGPSに登録してあるのですが、上杉村道路元標、ちかくまで来ているのですが回りをウロウロしている様で、なかなか見つけられません。 もしやあそこに見える二宮金次郎像の前にあるのは!? 資料を確認すると間違いなさそうです、小学校の中庭の様なのですが、柵とかはありませんしどちらから回っても雪の中を行くしかなさそうですので、強行突破です。 さすがにスパッツまでは用意していませんでしたが、替えのニッカホースもありますし、案の定50cm位は埋まってしまいました。  10時55分、今日6つ目の美守村道路元標までやってきました。 次の大瀁村道路元標まで6キロ程の距離なのですが、帰りの時間が迫ってきました、直江津駅1312発の北陸本線経由にするか、名古屋から近鉄利用になりますが1311発で長野~松本経由にするか、いずれにしてもパンクとかアクシデントを考えるとこれ以上足を伸ばすのは難しいので直江津方面へ向かう事にします。 それに大瀁村道路元標近くには今は無き頚城鉄道の車両などが保存されている処もあるとか、次の機会の愉しみとします。
10時55分、今日6つ目の美守村道路元標までやってきました。 次の大瀁村道路元標まで6キロ程の距離なのですが、帰りの時間が迫ってきました、直江津駅1312発の北陸本線経由にするか、名古屋から近鉄利用になりますが1311発で長野~松本経由にするか、いずれにしてもパンクとかアクシデントを考えるとこれ以上足を伸ばすのは難しいので直江津方面へ向かう事にします。 それに大瀁村道路元標近くには今は無き頚城鉄道の車両などが保存されている処もあるとか、次の機会の愉しみとします。  市街のイトーヨーカドーで食料を調達して直江津駅へ、昨日と同じルートも何なので、長野経由をとる事にします。 しかし駅構内は鉄どもでごった返しています、高級デジイチを首からぶら提げ、手には三脚、中には脚立まで用意しているつわものも、ホームや車内を走り回り、視線がおかしい、概ね格好がダサい、一目瞭然です。 それにつけ込んでJRも商売上手で「ありがとう信越線」なる全席指定の臨時列車まで運転する始末。
市街のイトーヨーカドーで食料を調達して直江津駅へ、昨日と同じルートも何なので、長野経由をとる事にします。 しかし駅構内は鉄どもでごった返しています、高級デジイチを首からぶら提げ、手には三脚、中には脚立まで用意しているつわものも、ホームや車内を走り回り、視線がおかしい、概ね格好がダサい、一目瞭然です。 それにつけ込んでJRも商売上手で「ありがとう信越線」なる全席指定の臨時列車まで運転する始末。  長野までは座れましたが長野~松本間は座れず、写真は姨捨駅から望む善光寺平、上越と比べると雪は少ない様です。 ところで日本三大車窓って後2つはどこだっけ? 疑問があればすぐにググれる便利な世の中になったものです、「狩勝峠」と「矢岳越え」だそうです、納得。
長野までは座れましたが長野~松本間は座れず、写真は姨捨駅から望む善光寺平、上越と比べると雪は少ない様です。 ところで日本三大車窓って後2つはどこだっけ? 疑問があればすぐにググれる便利な世の中になったものです、「狩勝峠」と「矢岳越え」だそうです、納得。  中津川駅でのホーム違い4分の乗換えをこなしな名古屋駅へ、ここで下りる階段を間違えるととんでもない遠回りになりますので、広小路口側へ下りて近鉄との連絡口へ、14分と時間の余裕はあったのですが、3分台で伊勢中川行き急行へ、座れはしませんでしたが輪行袋の置き場所も確保、まだ2回乗り換え2時40分もありますが、近鉄電車に乗り込んだら帰ってきたも同然。
中津川駅でのホーム違い4分の乗換えをこなしな名古屋駅へ、ここで下りる階段を間違えるととんでもない遠回りになりますので、広小路口側へ下りて近鉄との連絡口へ、14分と時間の余裕はあったのですが、3分台で伊勢中川行き急行へ、座れはしませんでしたが輪行袋の置き場所も確保、まだ2回乗り換え2時40分もありますが、近鉄電車に乗り込んだら帰ってきたも同然。 【1024】 新潟県 中頚城郡 高士村 (現 上越市)
【1025】 新潟県 中頚城郡 櫛池村 (現 上越市)
【1026】 新潟県 中頚城郡 上杉村 (現 上越市)
【1027】 新潟県 中頚城郡 美守村 (現 上越市)