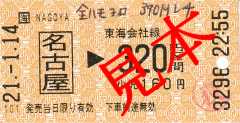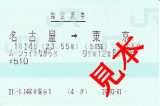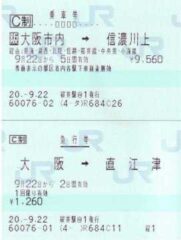再び常磐線を北上していわきから磐越東線へ、磐越西線には何度か乗っていますが、郡山以東の東線は初めてです。 神俣駅で下車し滝根村道路元標へ。 25分で次の列車に乗り郡山へ、再び水郡線に乗り、今日は棚倉町道路元標のある磐城棚倉駅まで往復の予定だったのですが…←磐越東線神俣駅道路元標探索には現存情報をノートPCに入れていますし、予定している場所は地図をプリントアウトして持って行く他、ハンディGPSにもウェイポイントとして登録してあるのですが… 福島県東白川郡の棚倉町道路元標を尋ねて磐城棚倉駅を下車、プリントアウトした地図に従って目的地に向かいますが、何故かハンディGPSの示す位置と違うのです、距離で1キロ余り、駅からの方角だと全く反対になってます。 ひとつは街の中心から少し外れた神社の鳥居の前、もうひとつは街の中心に近いそれっぽい場所、いずれかが間違って登録しているか、オンライン地図の印刷時に中心点をずらせてしまったのか、道路元標が移設されたかして参考にしている複数の現存情報にズレがあったのか。 その場でノートPCを起動して情報を再確認すればよいのですが、次の列車への時間が微妙なので、GPSの示す街の中心に近いポイントに引き返したものの、道路元標やらしき場所も見当たりません、ぐずぐずしている内に列車の時間が迫ってきて、仕方なく1本送らせる事にしてノートPCを開く事に。 どうやら先の神社前が正しかった様で、そちらへ向かう事にしましたが、なんと次の列車は2時間先。 まぁのんびり道路元標を尋ねて、この山あいの盆地の街で昼食でもする事にします。
再び常磐線を北上していわきから磐越東線へ、磐越西線には何度か乗っていますが、郡山以東の東線は初めてです。 神俣駅で下車し滝根村道路元標へ。 25分で次の列車に乗り郡山へ、再び水郡線に乗り、今日は棚倉町道路元標のある磐城棚倉駅まで往復の予定だったのですが…←磐越東線神俣駅道路元標探索には現存情報をノートPCに入れていますし、予定している場所は地図をプリントアウトして持って行く他、ハンディGPSにもウェイポイントとして登録してあるのですが… 福島県東白川郡の棚倉町道路元標を尋ねて磐城棚倉駅を下車、プリントアウトした地図に従って目的地に向かいますが、何故かハンディGPSの示す位置と違うのです、距離で1キロ余り、駅からの方角だと全く反対になってます。 ひとつは街の中心から少し外れた神社の鳥居の前、もうひとつは街の中心に近いそれっぽい場所、いずれかが間違って登録しているか、オンライン地図の印刷時に中心点をずらせてしまったのか、道路元標が移設されたかして参考にしている複数の現存情報にズレがあったのか。 その場でノートPCを起動して情報を再確認すればよいのですが、次の列車への時間が微妙なので、GPSの示す街の中心に近いポイントに引き返したものの、道路元標やらしき場所も見当たりません、ぐずぐずしている内に列車の時間が迫ってきて、仕方なく1本送らせる事にしてノートPCを開く事に。 どうやら先の神社前が正しかった様で、そちらへ向かう事にしましたが、なんと次の列車は2時間先。 まぁのんびり道路元標を尋ねて、この山あいの盆地の街で昼食でもする事にします。
 ← 棚倉城址、丹羽長秀の息子が江戸時代初期に築城して、戊辰戦争で板垣退助に攻め落とされたそうです、立派な石垣こそありませんが規模の割りにしっかりした堀が残っています。 城址内には町立図書館があったので時間潰しも兼ねて立ち寄ってみます、県告示の棚倉町道路元標の字番地を調べると、やはり先の神社前になっていて、移動はしていない様で、どうやら間違いはハンディGPSへデータを転送したカシミールへの登録間違いだった様です。 図書館で色々見ているとここ棚倉からは東北本線の白河へJRバスの路線があって、それも1時間に1?2本も出ている様です、これ利用すると水郡線で郡山へ戻らずとも、2時間の遅れを回復できそうです、大急ぎで図書館を後にしバス停へ。
← 棚倉城址、丹羽長秀の息子が江戸時代初期に築城して、戊辰戦争で板垣退助に攻め落とされたそうです、立派な石垣こそありませんが規模の割りにしっかりした堀が残っています。 城址内には町立図書館があったので時間潰しも兼ねて立ち寄ってみます、県告示の棚倉町道路元標の字番地を調べると、やはり先の神社前になっていて、移動はしていない様で、どうやら間違いはハンディGPSへデータを転送したカシミールへの登録間違いだった様です。 図書館で色々見ているとここ棚倉からは東北本線の白河へJRバスの路線があって、それも1時間に1?2本も出ている様です、これ利用すると水郡線で郡山へ戻らずとも、2時間の遅れを回復できそうです、大急ぎで図書館を後にしバス停へ。
 棚倉と白河を結ぶJRバスは白棚(はくほう)線と云って、国鉄の廃線跡の専用道を利用していました、ただJRバスの地方路線にしては本数が多いので五新線の様に一般車が入ってきたり自転車で走ったりなんて事はできそうにありません、間違って走って出くわすと高野山の南海バス専用道の様に怒鳴られる事請け合いです。 それに一般道との交差は専用道優先の様です、踏切こそありませんが。 ところで棚倉町へは時間の掛かる水郡線を利用するよりも東北新幹線の駅もある新白河からこのバスを利用する方が安くて早い様なのです。
棚倉と白河を結ぶJRバスは白棚(はくほう)線と云って、国鉄の廃線跡の専用道を利用していました、ただJRバスの地方路線にしては本数が多いので五新線の様に一般車が入ってきたり自転車で走ったりなんて事はできそうにありません、間違って走って出くわすと高野山の南海バス専用道の様に怒鳴られる事請け合いです。 それに一般道との交差は専用道優先の様です、踏切こそありませんが。 ところで棚倉町へは時間の掛かる水郡線を利用するよりも東北新幹線の駅もある新白河からこのバスを利用する方が安くて早い様なのです。
 ハンディGPSのデータを見ていると白棚線沿線にも道路元標がある様で、調べて見ると福島県西白河郡の金山村道路元標が、それもバス停から適当な距離、次のバスへは1時間ありますが、再び乗る機会があるか判らないバス路線、これは途中下車しない訳には行きません、転んでもタダでは起きません。 ← 雪が積もっていると吹き溜まりの様な処にある道路元標探索には不利ですが、雪をなすりつけてやるとご覧の様に、でも気温が高いとすぐに溶けてしまうので、いつもうまく行くとはいかない様です。
ハンディGPSのデータを見ていると白棚線沿線にも道路元標がある様で、調べて見ると福島県西白河郡の金山村道路元標が、それもバス停から適当な距離、次のバスへは1時間ありますが、再び乗る機会があるか判らないバス路線、これは途中下車しない訳には行きません、転んでもタダでは起きません。 ← 雪が積もっていると吹き溜まりの様な処にある道路元標探索には不利ですが、雪をなすりつけてやるとご覧の様に、でも気温が高いとすぐに溶けてしまうので、いつもうまく行くとはいかない様です。
 結局、棚倉では食事をする時間はなかったので、次のバスを待つ間に適当な店が無いかと探すと、「手打中華」なる店が、東日本へ来るとそばやうどんの黒いつゆには閉口するのですが、ラーメンならば(^_^;) チャーシュータンメンを戴きます、チャーシューそのものは今一つでしたが、麺もスープもなかなか美味しかったです。
結局、棚倉では食事をする時間はなかったので、次のバスを待つ間に適当な店が無いかと探すと、「手打中華」なる店が、東日本へ来るとそばやうどんの黒いつゆには閉口するのですが、ラーメンならば(^_^;) チャーシュータンメンを戴きます、チャーシューそのものは今一つでしたが、麺もスープもなかなか美味しかったです。
 東北本線新白河から東北本線に乗車、栃木県に入り黒田原駅で下車、那須郡の那須村道路元標を尋ねます。
東北本線新白河から東北本線に乗車、栃木県に入り黒田原駅で下車、那須郡の那須村道路元標を尋ねます。
← 古い街並に廃郵便局舎、黒田原郵便局
 今も営業しているのか、いないのか判らない様な自転車屋のすすけたショーウィンドの中に PEUGEOT が、私は旧車やオールドパーツの目利きはできないので価値の程は?
今も営業しているのか、いないのか判らない様な自転車屋のすすけたショーウィンドの中に PEUGEOT が、私は旧車やオールドパーツの目利きはできないので価値の程は?
 今夜は群馬県の前橋泊まりなので、小山から両毛線へ乗換えるのですが、両毛線は伊勢崎近くで踏切事故があった様で運休や遅れがでている模様、その上高崎線でも人身事故で遅れがでている様です。 とにかく両毛線は30分以内の遅れで運転はされている様で無事に前橋へ、実は両毛線は未踏区間でして、これで沖縄を除く46都道府県の全ての県庁所在地に降り立った事になりました。
今夜は群馬県の前橋泊まりなので、小山から両毛線へ乗換えるのですが、両毛線は伊勢崎近くで踏切事故があった様で運休や遅れがでている模様、その上高崎線でも人身事故で遅れがでている様です。 とにかく両毛線は30分以内の遅れで運転はされている様で無事に前橋へ、実は両毛線は未踏区間でして、これで沖縄を除く46都道府県の全ての県庁所在地に降り立った事になりました。
← 前橋駅にて、一部の列車には湘南色の115系が健在でした。