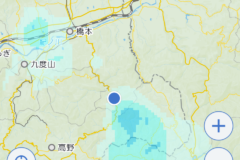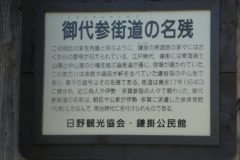何事もなければ4時過ぎまで仮眠をしてられるのですが、好事磨多しとは良く云ったもので、案の定 0245に起こされます。とにかく橿原市の勤務先を 0839 にスタート、飛鳥川べりから下ッ道(中街道)を北上、環濠集落で知られる稗田町を過ぎた辺りで佐保川沿いに入り、平城宮跡の中を突っ切ってJR平城山(ならやま)駅付近で京都府に入ります。京奈和自転車道のルートになっていて最近ようやく案内の標識が整備されつつあります。とにかく一番楽に府県境を越える事ができます。
何事もなければ4時過ぎまで仮眠をしてられるのですが、好事磨多しとは良く云ったもので、案の定 0245に起こされます。とにかく橿原市の勤務先を 0839 にスタート、飛鳥川べりから下ッ道(中街道)を北上、環濠集落で知られる稗田町を過ぎた辺りで佐保川沿いに入り、平城宮跡の中を突っ切ってJR平城山(ならやま)駅付近で京都府に入ります。京奈和自転車道のルートになっていて最近ようやく案内の標識が整備されつつあります。とにかく一番楽に府県境を越える事ができます。 木津川左岸に出て 1115 恭仁(くに)大橋で右岸に渡り、府県道5号木津信楽線に入りますが、休日とあってローディの多い事。1155 お馴染み和束のローソンで補給を兼ねて小休止。
木津川左岸に出て 1115 恭仁(くに)大橋で右岸に渡り、府県道5号木津信楽線に入りますが、休日とあってローディの多い事。1155 お馴染み和束のローソンで補給を兼ねて小休止。

和束と湯舟の間のトンネルを過ぎた辺りで、niwa-chanさんがお出迎えに来てくれました、場所も時間も決めてなかったのですが、コースの見当はついているのでKHSを駆ってここまで下ってきてくれました。いつもは府県道5号を信楽町神山まで越えるのですが、今日はniwa-chanさんの案内で朝宮へ標高323m程の無名の峠越えます。実は裏白峠の西側に越える穀池峠は越えた事はあるのですが、こちらは初めてなのです。R477に入る処でniwa-chanさんとお別れし瀬田に向かって長いダウンヒルです。


1326 瀬田川と合流する鹿跳(ししとび)橋へ、滋賀県に強風注意報が出ていると聞いたのですが、向かい風でなかなか前に進みません、瀬田の唐橋近くで小休止(写真左)。時間もないので今回は「茶丈藤村」はパスして左岸の「夕照の道」の道を行きます。ところで琵琶湖周辺の湖岸緑地は「コロナ禍」でことごとくキャンプ禁止になっているのですが、帰帆島前後はOKらしく結構な人出です。しかし湖岸道路は最悪の向かい風、後でショコラ氏に教えて貰ったのですが、この風だと内側の「メロン街道」(農免道路)を走った方が楽かもとか。琵琶湖大橋を渡り対岸の湖西側は多少マシな事を願うばかり。16時前に大橋を渡りきり再び大津市に。 いわゆる「びわいち」ルートを逆打ちするのは初めてなんですが、対向車線路肩のブルーラインを頼りに走ります。時間的にも「びわいち」も終盤とおぼしきサイクリストが次々とやってきます、17時前にはどうにか蓬莱浜を通過、あまり暗くならない内に大型車の多いR161を抜けだしたいものです。白髭神社を過ぎ湖岸道路を避けて県道558号高島大津線を北上し、1840 安曇川町のバローに立ち寄って買出しを済ませた頃にはもう真っ暗、ナイトランは覚悟の上ですのでライト等の装備は完璧ですが「六ッ矢崎浜オートキャンプ場」に着いたのは1939 ですから休憩込みで10時間の道のり、17時頃には着いていた一行と無事に合流する事ができました。
いわゆる「びわいち」ルートを逆打ちするのは初めてなんですが、対向車線路肩のブルーラインを頼りに走ります。時間的にも「びわいち」も終盤とおぼしきサイクリストが次々とやってきます、17時前にはどうにか蓬莱浜を通過、あまり暗くならない内に大型車の多いR161を抜けだしたいものです。白髭神社を過ぎ湖岸道路を避けて県道558号高島大津線を北上し、1840 安曇川町のバローに立ち寄って買出しを済ませた頃にはもう真っ暗、ナイトランは覚悟の上ですのでライト等の装備は完璧ですが「六ッ矢崎浜オートキャンプ場」に着いたのは1939 ですから休憩込みで10時間の道のり、17時頃には着いていた一行と無事に合流する事ができました。
既に宴の準備はできているので、お二人に手伝ってもらってテントを設営します。一行は最初湖岸よりにテントを設営したものの、あまりに風が強いので木立の中で宴を初めていたとの事、私は木立の中に設営する事にしたので、結局は二人も木立の中へ引っ越しする事に、すぐ横が道路なのですが、夜も更けると意外に静かです。

酒だけ積んできた私ですが、ショコラシェフと齋藤さんのお陰で満腹満足の夜が更けて行きます、暫くは「月うさぎキャンプ」や「笠置キャンプ場」での大人数でのキャンプは憚られるご時世ですが、それはそれで少人数でのキャンプを暫くは愉しむ事も良いでしょう。
本日の走行134.4キロ、所要時間8時45分、平均速度15.3km/h。
明日は4サイドを3台連ねて堅田まで走る予定です。