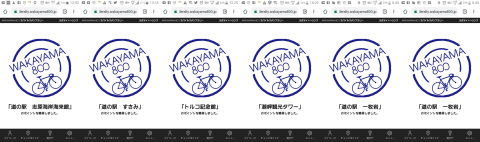暮れにやってきたデモンタ用に筒型タイプの輪行袋を新調しました。なんと自転車人生10個目の輪行袋になってしまいました。マルトのRINKO BAG ZDですが探してみるとモノタロウが一番安かったのですが、箱が傷んでいると云う訳あり品で送料込み3,300円で手に入れる事ができました、しかし箱入りの輪行袋って初めてですわ。
暮れにやってきたデモンタ用に筒型タイプの輪行袋を新調しました。なんと自転車人生10個目の輪行袋になってしまいました。マルトのRINKO BAG ZDですが探してみるとモノタロウが一番安かったのですが、箱が傷んでいると云う訳あり品で送料込み3,300円で手に入れる事ができました、しかし箱入りの輪行袋って初めてですわ。

 9代目なんと1970~80年代でしょうかSS印ヤングマン輪行袋、非常に状態の良い新品を今年の正月にTさんから頂きました。このサイズの輪行袋、asuka号をヘッド抜き輪行ができる様に改造してから、私も今の処は使い道がないのですが、輪行袋より収納袋が簡易サドルバッグに使えそう。
9代目なんと1970~80年代でしょうかSS印ヤングマン輪行袋、非常に状態の良い新品を今年の正月にTさんから頂きました。このサイズの輪行袋、asuka号をヘッド抜き輪行ができる様に改造してから、私も今の処は使い道がないのですが、輪行袋より収納袋が簡易サドルバッグに使えそう。
 8代目は2018年10月の「紀伊半島ツーリング」の折に輪行袋を忘れていって、紀伊田辺で買い求めたオーストリッチの巾着タイプのL-100、それまで使っていた同じくオーストリッチのemu(左から3番目)の縫製があまりに酷くてファスナーの縫い付け部分が次々とほつれてきてファスナーに噛みこむので、輪行の度に買い替え様と思っていた矢先でした。しかしこのemu、同じカラーを使っている人がFacebookにいて、やはりほつれてきているそうでロット不良でしょうね、昨今の中国製品の方がずっとマシと思える品質ですね、収納袋の底も抜けてしまいました。おかげで今はL-100が主力になっています。
8代目は2018年10月の「紀伊半島ツーリング」の折に輪行袋を忘れていって、紀伊田辺で買い求めたオーストリッチの巾着タイプのL-100、それまで使っていた同じくオーストリッチのemu(左から3番目)の縫製があまりに酷くてファスナーの縫い付け部分が次々とほつれてきてファスナーに噛みこむので、輪行の度に買い替え様と思っていた矢先でした。しかしこのemu、同じカラーを使っている人がFacebookにいて、やはりほつれてきているそうでロット不良でしょうね、昨今の中国製品の方がずっとマシと思える品質ですね、収納袋の底も抜けてしまいました。おかげで今はL-100が主力になっています。
 実は2015年に「自転車人生6個目の輪行袋」なる記事を書いたのですが、実はオーストリッチの紫色の前に青色のものを使っていたので、その時点で7個目だった計算に。
実は2015年に「自転車人生6個目の輪行袋」なる記事を書いたのですが、実はオーストリッチの紫色の前に青色のものを使っていたので、その時点で7個目だった計算に。
写真は1991年8月に紀勢本線賀田駅にて、R311の全通前で賀田~二木島駅間の一駅だけ輪行した思い出が、輪行には手回り品切符が要った時代ですが、車掌さんに料金だけ払った記憶が。
 さてデモンタ用の筒型輪行袋、本来は小径車用の様ですが、650Aのデモンタもすっぽり被さります。3本のコードで縛る様にできていますが、ファスナーもマチもないのでミシンさえあれば誰でも作れそうな気もしますけど。自転車の一部が出ている輪行は駄目だなんて野暮は云わないでね。
さてデモンタ用の筒型輪行袋、本来は小径車用の様ですが、650Aのデモンタもすっぽり被さります。3本のコードで縛る様にできていますが、ファスナーもマチもないのでミシンさえあれば誰でも作れそうな気もしますけど。自転車の一部が出ている輪行は駄目だなんて野暮は云わないでね。